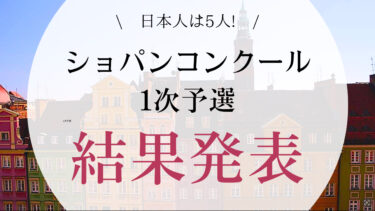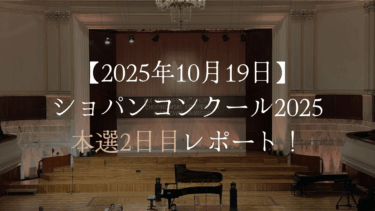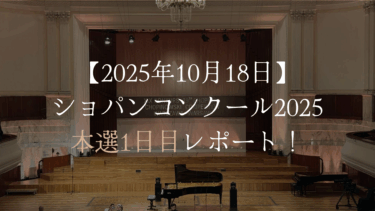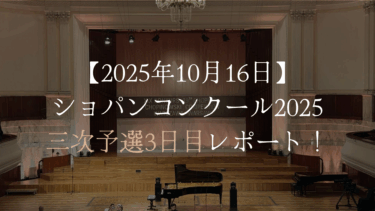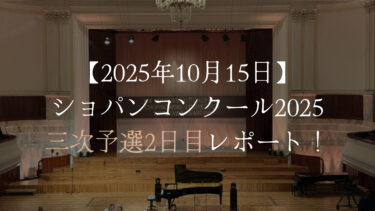ショパン音楽教室 編集部 末次弘季
第19回ショパン国際ピアノコンクール2025の二次予選2日目。秋の冷たさと、熱気を帯びた若きピアニストたちの息遣いが交錯する、特別な一日だった。第2予選の2日目は、アジア勢を中心とした多彩な顔ぶれ。中国、カナダ、ポーランド、韓国、そして日本。それぞれが異なるショパン像を抱えていた。
この日は午前にエリック・グオ(カナダ)、シャオユ・フー(中国)、ズーハン・ジン(中国)、アダム・カウドゥンスキ(ポーランド)、
二日目のステージは、テクニックの競演ではなく、それぞれの「人生観」としてのショパンが響き合う時間となった。技巧よりも詩情、外面的な輝きよりも内なる光。この日の舞台には、そんな美学が一貫して流れていた。
末次 弘季
現地ワルシャワ在住のピアニスト末次弘季です。
10:00 (CEST) エリック・グオ(23)カナダ🇨🇦
マズルカは「ピアニストの真の姿を映すレンズ」– Eric Guo
選択したピアノ: Steinway & Sons
VIDEO
◉ Eric Guo 2次予選プログラム
ポロネーズ 嬰ヘ短調 作品44
エチュード 変ホ短調 作品10-6
前奏曲 第19番〜第24番(変ホ長調〜ニ短調)作品28
マズルカ 第1〜4番(変ロ長調・ホ短調・変イ長調・イ短調)作品17
前奏曲 嬰ハ短調 作品45
舟歌 嬰ヘ長調 作品60
◉プロフィール(Eric Guo)
師事:Jonathan Biss, Anton Nel
所属:グレン・グールド音楽学校(トロント王立音楽院附属)
受賞歴:2023年第2回ショパン国際ピリオド楽器コンクール優勝およびマズルカ賞
その他:近年は「ショパンとその時代」音楽祭(ワルシャワ)やドゥシニキ音楽祭など、ポーランド主要音楽祭で頻繁に招かれる。
レポート 3次予選通過予想: ★★★★
グオの音楽は、単なる再現ではなく「内なる語り」の芸術である。 《ポロネーズ嬰ヘ短調》の冒頭から響いた低音は、武骨な力ではなく、柔らかく沈潜する抒情を孕んでいた。
フォルティッシモの一点に頼らず、ひとつの音から無限の陰影を彫り出す——まるで古いレコードの針先が、記憶の奥に刻まれた感情をすくい取るような精妙さ。全体の構築は驚くほど自然で、音楽が呼吸をしているかのようだ。
そして圧巻は《マズルカ作品17》の連なり。リズムの起伏は控えめでありながら、各曲の内部で息づくテンポ・ルバートの揺らぎが、まるでポーランドの大地の呼吸そのもののように感じられた。とりわけ第4番イ短調の沈黙の美学は、まさに心の琴線を震わせる瞬間だった。グオ自身が語るように、マズルカは「ピアニストの真の姿を映すレンズ」であり、その一音一音には、喜びと郷愁、そしてショパンへの祈りが滲んでいた。
後半の《前奏曲嬰ハ短調 作品45》と《舟歌作品60》は、時間が溶けていくようなトランス状態を作り出した。一音の立ち上がりがまるで水面に光が射す瞬間のようで、そこから柔らかな残響が広がる。技巧を誇示することなく、音の密度だけで場を支配する。終盤、舟が静かに遠ざかるように音が消えていった瞬間、ホール全体が息を呑んでいた。——それは演奏というよりも、ひとつの「祈りの儀式」であった。
10:55 (CEST) シャオユー・フー(20)中国🇨🇳
煌びやかなFazioliサウンド– Xiaoyu Hu
◉ Eric Guo 2次予選プログラム
ポロネーズ 嬰ヘ短調 作品44
前奏曲 第13〜18番(嬰ヘ長調〜ヘ短調)作品28
バラード 変イ長調 作品47
ロンド 変ホ長調 作品16
◉プロフィール(Xiaoyu Hu)
師事:Misha Namirovsky
所属:中央音楽学院(北京)
受賞歴:深圳国際ピアノコンクール第1位、第15回イルムラー国際ピアノコンクール第1位
これまでに共演:青島フィルハーモニー、上海歌劇院交響楽団、杭州フィル、武漢フィルほか
マスタークラス:Angela Hewitt, Matti Raekalio, Jörg Demus, Yukio Yokoyama, Robert Shannon
9歳で上海音楽学院附属中学に入学、早くから国内外の注目を集める
レポート 3次予選通過予想: ★★★★
フー・シャオユーの音には、まるで研ぎ澄まされたクリスタルのような透明な純度がある。朝のフィルハーモニーの空気を裂く最初の和音から、聴衆はその音色の煌びやかさに惹き込まれた。
《ポロネーズ嬰ヘ短調》では、伝統的な力強さや重厚さではなく、端正で幾何学的な均衡を保った演奏を披露。低音の響きは硬質だが、決して冷たくない。彼の指先からは、音そのものが光の粒子のようにこぼれ落ちていく。中盤に置かれた《前奏曲作品28》第13〜18番では、彼の音楽的思考の明晰さが際立った。
とりわけ《第15番 変ニ長調(雨だれ)》における音色の変化は見事で、ペダルと指のバランスを極限まで緻密にコントロールしながら、音が空間の中で静かに振動するように響く。ファツィオリの軽やかなタッチを最大限に生かし、各声部の透明度が際立その音の清澄さは、まるで磨き上げられたガラスに水滴が落ちて広がる瞬間を見ているようだ。
《バラード変イ長調》では一転、繊細な詩情が花開く。ロマン派的な大仰さを避け、まるで自らの呼吸に合わせてストーリーを紡ぐような自然な流れ。フレーズの終わりに残る沈黙までもが音楽の一部であり、そこに漂うわずかな間が、彼の音楽の最大の魅力である“間の美学”を物語っていた。
そして最後の《ロンド変ホ長調》では、すべての音が輝きと遊び心に満ちていた。軽やかな音型の中に一切の無駄がなく、リズムは弾むように自在。その清潔なテクスチュアと余裕ある解釈が、彼の年齢を忘れさせる成熟を示していた。
11:45 (CEST) ズーハン・ジン(16)中国🇨🇳
選択したピアノ:Steinway & Sons
VIDEO
◉ 2次予選プログラム
スケルツォ ホ長調 作品54
前奏曲 第1〜16番(ハ長調〜変ロ短調)作品28
ポロネーズ 変イ長調 作品53 《英雄》
◉プロフィール(Zihan Jin)
師事:Yun Sun
所属:上海音楽学院附属中学
受賞歴:
共演:無錫交響楽団、ハルビン交響楽団、上海歌劇院交響楽団、杭州フィル、武漢フィル
レポート 3次予選通過予想: ★★★
ズーハン・ジン――わずか16歳とは思えぬほどの完成度と集中力。ステージに立つ彼の姿からは、若者特有の無垢さよりもむしろ職人的な緊張感 が漂っていた。
《前奏曲集 作品28》第1〜16番は、彼の構築美が最も際立つセクションだった。テンポの選択、ペダルの処理、音のバランス――どれも信じられないほど冷静で、16歳という年齢を完全に超越している。特に《第8番 嬰ヘ短調》では、緊張感の中に浮かぶ柔らかな陰影が印象的で、まるで光を反射する氷の彫刻 のように音楽が形を変えていく。終盤に向かって構築されていく静謐なクレッシェンドには、彼の中に眠るロマンティックな心の片鱗が垣間見えた。
最後の《ポロネーズ 変イ長調〈英雄〉》――怒りのような熱情冷たい光で燃える 演奏。
その他
ポーランドメディアのレビューでは、「彼の《前奏曲集》は驚くほど緻密で、音楽を幾何学的に捉える天才の冷静さを感じた。
インタビューで本人は、「自分の音は“感情の反射”だと思っています。ショパンの音楽は、感情をそのまま表現するのではなく、光が鏡に当たって跳ね返るように心を映す――そう感じます」と語っている。
――若き天才はまだ“燃える”ことを知らない。だが、冷たく輝くその光は、確実に未来の炎 を予感させた。
12:55 (CEST) アダム・カウドゥンスキ(29)from ポーランド🇵🇱
一つの人生を描いた連作詩 –Adam Kałduński
選択したピアノ:Steinway & Sons
VIDEO
◉ 2次予選プログラム
《24の前奏曲》 作品28(第1〜第24番)
《ポロネーズ 変イ長調》 作品53《英雄》
◉プロフィール(Adam Kałduński)
師事:師事:Katarzyna Popowa-Zydroń, Jerzy Sulikowski
学歴:フェリクス・ノヴォヴィエスキ音楽大学(ビドゴシチ)卒業
受賞歴:第2回北京ショパン国際青少年ピアノコンクール優勝(2019)、
マスタークラス受講歴:Dang Thai Son, Arie Vardi, Nikolai Demidenko, Edward Auer, Kevin Kenner, Tamás Ungár, Dina Yoffe
近年の活動:ワルシャワ・フィル、カトヴィツェのNOSPR、ビドゴシチのポメラニア・フィル、ドゥシニキ=ズドルイのショパン音楽祭などで演奏
レポート 3次予選通過予想: ★★★★
カウドゥンスキの音楽には、沈黙の中に宿る意志 がある。彼は、いわゆる派手な「ショパン的美」ではなく、ひとつひとつの音を彫り込むようにして、“作品そのものの呼吸”を形にしていく。
《24の前奏曲》は、まさに“旅”だった。それも疾走する旅ではなく、記憶を辿るような、静かで内省的な巡礼のような。
特筆すべきは、間の使い方 である。音と音の間に存在する“無音”にこそ、最も豊かな音楽が宿っている。彼の指が鍵盤から離れた瞬間に生まれる沈黙が、まるで遠くの鐘の余韻のように会場の空気を震わせた。その静寂は決して偶然ではなく、彼自身が丁寧に設計した構築の芸術 だ。
そして《ポロネーズ変イ長調〈英雄〉》。
《第8番 嬰ヘ短調》での緊張など、正確性
その他
カウドゥンスキはインタビューでこう語っている。「僕のいちばん誠実な教師は……録音機だよ。」
長年、レッスンを離れ、自身の演奏を録音しては聴き直し、分析し、再構築するという作業を繰り返しているという。「完璧には到達できない。けれど、近づこうとする過程こそが芸術だ。」この言葉が、彼の《前奏曲集》の演奏そのものを象徴している。
ポーランドの音楽誌では、彼のステージを「緻密な構築と深い詩情の融合」と評し、Program 2の評論家Marcin Majchrowskiも「彼は既に完成された芸術家。勝つためにではなく、語るために弾いている」と述べている。一方でAndrzej Sułekは、「彼の演奏は美しいが、あまりにも誠実すぎる。勝負に出る大胆さをもう少し望みたい」と語った。
しかし私は思う。カウドゥンスキの音楽は、競争ではなく“告白”である。鍵盤の上で彼が求めているのは栄冠ではなく、音の中に潜む真実の静けさ なのだ。
13:45 (CEST) ダヴィド・フリクリ(24)ジョージア🇬🇪
厚みのある大地の温度と、祈りに似た優しさ – David Khrikuli
VIDEO
◉ 2次予選プログラム
《ポロネーズ 嬰ヘ短調》 作品44
《スケルツォ 嬰ハ短調》 作品39
《24の前奏曲》 作品28(第1〜第24番)
◉プロフィール(David Khrikuli)
David Khrikuli (ダヴィド・フリクリ)
師事:Stanislav Ioudenich
在籍:ソフィア王妃高等音楽院(マドリード)
受賞歴:カントゥ国際ピアノ・オーケストラコンクール(イタリア)第1位(2024)、
マスタークラス:Elisabeth Leonskaja, Rena Shereshevskaya, Nelson Goerner
共演:ジョージア・フィルハーモニー、イスラエル・カメラータ、モスクワ・フィル、イスラエル・フィルなど:
レポート 3次予選通過予想: ★★★★★
ダヴィド・フリクリの音楽には、厚みのある大地の温度と、祈りに似た優しさ がある。ステージに現れた彼の風貌は、まるで山岳の詩人のようで、その穏やかな微笑みがホールの緊張をほぐした。しかし、鍵盤に指を置いた瞬間、そこにはまるで別の人格が立ち上がる。
《ポロネーズ 嬰ヘ短調》の冒頭、深く沈み込む低音が鳴り響く。重さよりもまず“質量”を感じさせるその音は、心の奥底から湧き上がる民族的記憶 のようであった。中間部の弱音では、遠くの鐘が鳴るような静けさをたたえ、それがやがて感情の奔流へと変化していく過程に、聴衆は息を呑んだ。彼は豪放なタイプではない。だが、音の奥にある**“重力”を操る稀有な感性**を持っている。
続く《スケルツォ 嬰ハ短調》では、演奏全体が彼の人間性を映す鏡のようだった。華やかでありながら決して軽薄にならず、リズムの内側に柔らかな重心 がある。音の立ち上がりは鋭くとも、フレーズの終わりにはかならず温度が残る。その温度がホールの空気を包み、「技巧」と「情感」という二項が完全に調和していることを感じさせた。
そして圧巻は、最後に置かれた《前奏曲集 作品28》全曲。彼はこれらを24の断片的な小品ではなく、一編の壮大な物語 として描いた。《第1番》の透明な朝の光から、《第24番 ニ短調》の燃え尽きるような終止まで、全体に流れる呼吸はゆるやかで、ひとつの生命体の鼓動のように感じられた。音色の多彩さにも驚かされる。低音は湿った土のように重く、中音域には深い陰影があり、高音は霧のように溶けていく。特に《第20番 ハ短調》から《第24番》にかけての連続は、ほとんど宗教的な恍惚の境地に達していた。
その音楽は聴衆の心を掴み、離さない。決して派手ではないが、“人間の声”で語るショパン がそこにいた。終演後、ホールには長い沈黙が訪れ、それが次第に拍手へと変わった瞬間、彼が微笑みながら深く一礼した姿が忘れられない。
その他
演奏後のインタビューで彼はこう語っている。「このコンクールの舞台に立てることは、ショパンの歴史の一部になること。僕にとってそれは名誉であり、同時に責任です。」過去と現在が共鳴する聖堂 ”と形容した。
ポーランド国営ラジオの評論では、「彼の前奏曲集は、建築家のように構築されながらも、 詩人のように語る演奏だった」と絶賛されている。またDorota Szwarcmanは「彼の音は肉体的でありながら霊的だ」と評した。
――くまのような体格に宿る繊細な魂。その両極がひとつの身体に共存する奇跡。
17:00 (CEST) 桑原志織(30)日本🇯🇵
選択したピアノ:Steinway & Sons
VIDEO
◉プロフィール(桑原志織)
Shiori Kuwahara(桑原志織)
師事:Klaus Hellwig(ベルリン芸術大学)
学歴:東京藝術大学およびベルリン芸術大学を最優秀の成績で卒業
受賞歴:ベルリン・スタインウェイ賞(2022)
出演歴:ドゥシニキ=ズドルイ・ショパン音楽祭、プラハ・ルドルフィヌム、ヨーロッパ各国、日本、韓国、米国などで演奏活動
レポート 3次予選通過予想: ★★★★★
桑原志織のステージは、静けさのうちに始まり、そして静けさのうちに終わった。 だがその沈黙の間に、いくつもの宇宙が生まれ、消えていった。
冒頭の《舟歌 作品60》——彼女の世界では、この作品がただの抒情詩ではなく、時の流れそのもの として存在していた。精神的な重力 を帯びており、
続く《前奏曲》第13〜18番では、彼女の色彩感覚が際立った。変ホ短調では黒曜石のような深みを、変ニ長調(雨だれ)では、音が静かに地面に吸い込まれていくような感触を与えた。彼女の演奏は決して「美しい音」を目指すものではない。むしろ、音の裏側にある痛みや呼吸、そして沈黙 を聴かせようとする。その結果、音楽が「絵画」から「詩」へと変わる。
そして《幻想曲 ヘ短調》では、彼女の芸術の核心が現れた。感情の起伏は極端ではない。だがその抑制の中に、どこまでも深い情熱が燃えている。空間の使い方が驚くほど巧みで、フレーズの間に訪れる沈黙が、音以上に雄弁だった。まるで彼女の音楽は「呼吸の彫刻」であり、一つの和音が消えたあとも、その余韻が“時間の形”としてホールに残る。
ラストの《ポロネーズ〈英雄〉》。重厚な響きの中に、女性ならではの芯の強さがあった。堂々としたリズムの裏には、柔らかく揺れる哀しみが潜んでいる。この相反するエネルギーの共存こそが、彼女のショパンの本質だ。――強さと優しさ、情熱と沈黙。それらを併せ持つ音楽は、彼女自身の存在のように誠実で、揺るぎない。
その他
演奏後のインタビューで桑原はこう語った。「ショパンの音楽はとても感情的で、繊細です。 だからこそ、女性の方がその情緒の機微を表現できる部分もあると思います。」彼女は第2次予選に進出した8名の女性のひとりとして、「ここに立てることが光栄です。私には7人の“姉妹”がいるような気持ちです」と微笑んだ。
ポーランドメディア『PAP』は「彼女の《幻想曲》は、ホール全体を包み込むような空間の使い方で、音楽が建築物のように立ち上がっていった」と絶賛。また『Kurier Chopinowski』は「彼女の《舟歌》は、このステージの中でも最も詩的で洗練された瞬間のひとつだった」と記している。
――桑原志織のショパンは、激情の対極にある静けさの芸術。燃え上がる炎ではなく、夜の海を照らす微光のような音楽 。その静かな光が、ワルシャワの夜に長く残響していた。
17:55 (CEST) ヒョ・リー(18)韓国🇰🇷
ピアノではなく風を操っているよう – Hyo Lee
選択したピアノ:Shigeru kawai
VIDEO
◉プロフィール(Hyo Lee)
Hyo Lee(ヒョ・リー)
師事:Ewa Pobłocka(エヴァ・ポブウォツカ)
学歴:エコール・ノルマル音楽院(パリ)卒業(2024)
受賞歴:Astana Piano Passion国際コンクール入賞、
その他:兄のヒョク・リーと共に室内楽デュオとしても活動し、ベートーヴェン、ガーシュウィン、サン=サーンスなどを共演レパートリーに持つ
レポート 3次予選通過予想: ★★★★
ヒョ・リーは、この日のステージにおいて最年少ながら、精神的な成熟を感じさせる演奏 を聴かせた。彼のショパンは若さの煌めきよりも、むしろ沈着と構築の美学に貫かれている。ステージに現れたときの穏やかな表情からは、内に秘めた闘志が静かに燃えていることを感じた。
《ソナタ ハ短調》は、ショパンが18歳で書いた作品だが、ヒョの解釈は作曲者と同世代でありながら、その先の時代を見据えたかのように成熟していた。第1楽章ではクラシカルな均衡を保ちつつ、随所に挿し込まれるリタルダンドが、彼の音楽的直感の柔軟さを示す。テーマが再現する瞬間、空間の響きを見事に利用して、まるで一筆書きのように流れる自然な構造を作り出していた。
特に印象的だったのは、第3楽章。通常は軽やかなスケルツォ的性格で演奏されるが、ヒョはそれを内なる対話 のように静かに語り、透明な響きの中に、まだ少年である彼の「思考する沈黙」が聴こえた。彼は技巧よりも意味を重んじるピアニストであり、
後半の《前奏曲》第19〜24番では、音色の変化における敏感な呼吸感 が際立った。特に第23番ヘ長調で聴かせた柔らかなフレーズは、リズムを“保つ”というより、“漂わせる”という印象を残した。音の隙間に空気が入り込み、聴き手の心をやさしく揺らす。この感覚は、まるで彼がピアノではなく風を操っている かのようである。
ラストの《ポロネーズ〈英雄〉》では、音楽の輪郭をしっかりと捉えながらも、決して誇張に走らない品格があった。若者特有の勢いはあるが、それを完全にコントロール下に置き、一音一音に「選ばれた理由」が感じられた。フォルテでも決して荒れず、ホール全体を満たす重厚な響きの中に、どこか祈りのような純粋さが漂っていた。
ヒョの音楽はまだ「成長途中」にある。しかし、その未完成さの中にこそ、未来の巨匠を予感させる透き通った誠実さ が息づいている。彼のソナタは若きショパン自身へのオマージュであり、同時に、若き自分自身への手紙のようでもあった。
その他
ポーランドメディア『Rzeczpospolita』は、「彼のソナタは18歳のショパンが描いた若き理想を、 18歳のピアニストが現代の言葉で再構築したようだった」と評している。また『Wnet.fm』では「ヒョ・リーの演奏には、 驚くほどの集中力と、無垢な感情が同居していた」と紹介された。
兄のヒョク・リーが披露する成熟したドラマティズムとは対照的に、ヒョの音楽は“芽吹く瞬間の美しさ”を持っている。それは、まだ完全には咲いていない花が見せる、最も純粋で、最も尊い時間の輝きである。
18:45 (CEST) ヒョク・リー (25)韓国🇰🇷
選択したピアノ:Steinway & Sons
VIDEO
◉プロフィール(Hyuk Lee)
Hyuk Lee(ヒョク・リー)
師事:Vladimir Ovchinnikov(ウラジーミル・オフチニコフ)
学歴:エコール・ノルマル音楽院(パリ)卒
受賞歴:イグナツィ・ヤン・パデレフスキ国際ピアノコンクール(ビドゴシチ)第1位(2016)
出演歴:パリ・シャンゼリゼ劇場、ポーランド国立オペラ、プラハ・ルドルフィヌム、ブエノスアイレス・テアトロ・コロンなど世界各地で演奏
レポート 3次予選通過予想: ★★★★
ヒョク・リーのステージには、静かな自信と確固たる構築美 があった。すでに世界の檜舞台を経験してきた彼の演奏は、若々しさというよりも、むしろ老練な建築家が石を積み上げていくような安定感に満ちている。
《ポロネーズ 嬰ヘ短調》の冒頭、低音が響いた瞬間に、会場の空気が引き締まった。力強いが決して荒々しくない。一音一音に意思があり、剛と柔の境界線を正確に歩む演奏 だ。中間部のポリフォニックな絡みも極めて明晰で、形式的な堅牢さの中に“燃えるような内面の衝動”が潜んでいる。それはまるで、火山のマグマが地殻の奥で静かに熱を蓄えているような感覚だ。
続く《前奏曲》第7〜12番では、音色の選択とタイム・コントロールの緻密さが際立った。特に第9番ホ長調では、軽やかな左手のアルペッジョがまるで風のようにホールを通り抜け、高音域の響きが空間に淡く残る。一方で第12番嬰ト短調では、音の一粒一粒が鋼のように精密に磨かれ、全体の流れを劇的に収束させる。この冷静な構築力と内的な熱量のバランス こそ、ヒョクの真骨頂である。
《スケルツォ 変ロ短調》では、彼の音楽の核心が露わになる。この作品を「技巧の見せ場」としてではなく、“精神のドラマ”として描いた点に、彼の成熟を感じた。冒頭の閃光のようなパッセージのあとに続く静寂には、ただの間ではなく、哲学的な沈黙 があった。トリオ部分のカンタービレは格別で、祈りのように穏やかで、しかも揺るぎない。感情を誇張することなく、“語らないことで語る”演奏は、彼にしかできないものだろう。
そして《ソナタ〈葬送〉》。すでに2021年のファイナリストとして知られる彼だが、この日の演奏は、より深い人間的成熟を感じさせた。第1楽章の動機は明瞭に構築され、第2楽章のスケルツォでは稲妻のような緊張感を保ちながらも、決して音が硬くならない。そして第3楽章〈葬送行進曲〉——そのテンポは意外なほど抑制されており、すべてのフレーズが「語り」ではなく「追悼」として響いていた。終楽章の風のようなパッセージが消え入る瞬間、ホールはまるで息を止めていた。死ではなく“永遠”を聴かせた《葬送》だった。
ヒョク・リーのショパンは、激情ではなく「崇高さ」を目指している。音楽を支配することなく、音楽と共に歩む姿勢——それはまさに成熟した芸術家の証だ。この日の彼のステージは、静かな威厳に包まれた円熟の時間 であった。
その他
ポーランド紙『Rzeczpospolita』は、「ヒョク・リーは、技巧を超えて“語り”を実現した稀有なピアニスト。彼の《ソナタ変ロ短調》は、言葉を失わせる美しさだった」と評した。
演奏後のインタビューで、ヒョクは穏やかにこう語った。「僕にとってショパンは“感情”ではなく“祈り”です。ステージでは、いつも自分の人生の静かな部分を弾いているような気がします。」
兄ヒョとの対照も興味深い。ヒョが“未来へ向かう音”を奏でるなら、ヒョクは“過去を抱く音”を奏でる。二人の音楽が交錯する今大会は、まるで兄弟の対話そのものが、ショパンの物語として続いているかのようだ。
19:55 (CEST) クァンウク・リー(29)韓国🇰🇷
◉プロフィール(Kwanwook Lee)
Kwanwook Lee(クァンウク・リー)
師事:Alfred Perl(アルフレート・ペルル)
学歴:デトモルト音楽大学(Hochschule für Musik Detmold)在学
受賞歴:TBCピアノコンクール(韓国)第2位、
その他:ドイツ・デトモルトの州立劇場、ソウル・サミクアートホールなどで演奏。主にドイツを拠点に活動する。
レポート 3次予選通過予想: ★★★
クァンウク・リーのステージは、穏やかで誠実な音楽性に支えられた、「内省のリサイタル」であった。Yamahaの軽やかな音色を最大限に活かし、透明感のある音作りにこだわった姿勢は好印象である。
しかし一方で、この日の演奏全体にはどこか**“安全な美しさ”**が漂っていた。ショパンの音楽に潜むリスク、突発的な感情の閃き、あるいは崩れ落ちるような瞬間——そうした“危うさ”が少し不足していたようにも感じた。
《前奏曲》第13〜18番では、最初の数曲こそ音色の純度が際立っていた。特に第13番では透明で端正な響きが印象的で、ピアノというよりもハープのように清らかな音が会場を満たした。だが第16番の嵐のような激流では、構築がやや硬直し、拍の流れが自然さを欠いた。音の方向性がもう一歩“内側”に向かえば、より深い詩情に辿り着けただろう。
《バラード ヘ短調》では、音楽を大きく運ぶためのスケール感よりも、一音一音の美しさを大切にしている印象を受けた。
一方、《即興曲 変イ長調》から《アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ》への流れは見事だった。即興曲では自然な呼吸と柔軟なテンポ運びで、音楽が“語らずに語る”ような内面性を見せた。そのまま流れるように始まった《アンダンテ・スピアナート》では、Yamaha特有の明るい音が繊細に生き、“静けさの中の煌めき”を見せた。しかし「ポロネーズ」に入ると、やや表面的な勢いに傾き、音の層が平板化してしまったのは惜しい。力強さを出そうとするあまり、音の厚みよりも物理的な大きさ に頼ってしまった印象だ。
クァンウクの演奏は決して派手ではない。むしろ、音楽に誠実に向き合う姿勢が滲み出ていた。ただ、ショパンが求めたのは「正確さ」ではなく「真実」だとすれば、その一歩先の内なる熱 を、もう少し聴きたかった。彼の音楽は今、整いすぎている。そこにひと雫の“狂気”が混ざったとき、真に輝く瞬間が訪れるはずだ。
その他
『Rzeczpospolita』紙は、「アンダンテ・スピアナートの清潔な音と即興曲からの自然な繋がりは魅力的だったが、ポロネーズでの爆発的なエネルギーには欠けた」と評した。また『Kurier Chopinowski』は、「彼の音楽は透明で上品。しかし、あまりにも“安全”な解釈に終始した」と分析している。
だがこの“慎重さ”の裏には、ドイツで培われた構築的な音楽観が確かに息づいている。彼は感情を抑えることで、逆に音の純度を極限まで高めようとしているのだ。
20:45 (CEST) ティエンヨウ・リー(21) 中国 🇨🇳
選択したピアノ:Steinway & Sons
VIDEO
◉ 2次予選プログラム
《ソナタ ハ短調》 作品4
《ポロネーズ 変イ長調〈英雄〉》 作品53 《前奏曲》 作品28(第13〜18番:嬰ヘ長調〜ヘ短調)
◉プロフィール(Tianyou Li)
Tianyou Li(ティエンヨウ・リー)
師事:Xiaohan Wang(シャオハン・ワン)
学歴:天津音楽学院(Tianjin Conservatory of Music)在学 受賞歴:シンガポール国際ピアノコンクール第1位およびバッハ賞、 珠海モーツァルト国際コンクール第1位 スタインウェイ・アンド・サンズ・コンクール第2位、 北京ショパン国際青少年ピアノコンクール第3位 出演歴:ウィーン・ハイドンホール、北京国家大劇院、天津ジュリアード音楽院コンサートホール、 ベルリン・カンマームジークザールなど世界各地でリサイタルを開催。また、中国主要オーケストラやドイツ交響楽団ベルリン(Deutsches Symphonie-Orchester Berlin)と共演。
レポート 3次予選通過予想: ★★★★
この日最後に登場したティエンヨウ・リーの演奏は、一日の締めくくりにふさわしい静謐と覚醒のドラマ だった。彼の音楽は、若さゆえの大胆さではなく、むしろ「沈黙を知る若者」の深い内省に貫かれていた。
冒頭の《ソナタ ハ短調》では、18歳のショパンが描いた初期の理想を、21歳の青年が瑞々しく再構築する。形式的な端正さを保ちながらも、ティエンヨウの指先は常に“語り”を忘れない。第1楽章では、まるで霧の中から姿を現すようにテーマを導き、音の余韻を丹念に聴き取っていく。響きの制御力は驚異的で、ホールの空気を味方にする術を完全に心得ている。特筆すべきは、第4楽章の扱い方だ。この難曲を力で押すのではなく、むしろ肉体を“流体”のように使い、音を呼吸で操っていた。手首と腕の動きふぁ音楽の流れと一体化し、観客は彼の身体そのものが楽器になっていく様を目撃した。
《前奏曲》第13〜18番では、繊細さと決断力のバランスが見事に取れていた。第13番嬰ヘ長調の柔らかなアルペッジョは、まるで夜明けの空気のように澄み渡り、続く第14番変ホ短調では、内なる叫びを抑えきれない情熱がにじむ。特に第15番変ニ長調子〈雨だれ〉の中間部、沈黙を含んだピアノのタッチは絶妙で、響きの奥に“静けさそのものの声”が聴こえた。その瞬間、音楽は単なる演奏を超えて、詩を聴いているようだった 。
そして、《ポロネーズ〈英雄〉》。この作品で多くの若いピアニストが力任せに突き抜けていく中、ティエンヨウはまったく異なるアプローチを見せた。冒頭の和音は堂々としながらも決して重くなく、むしろ「歩み出す勇気」のように透明だった。中間部では細部のリズムを慎重に解釈し、テンポの推進力を自然に保ちながらも、フォルテの中にピアノの美学を忘れない 。彼の「英雄」は勝利の叫びではなく、耐え抜いた者の静かな微笑みだった。
演奏後、ホールには一瞬の沈黙が訪れた。拍手はその“間”のあとに、爆発的に湧き上がった。彼の音楽は、聴き手に「沈黙することの美しさ」を教えてくれる。若干21歳にして、この境地に到達していること自体が驚異だ。間違いなく、今大会の 最も詩的な演奏のひとつである。
その他
ポーランド公共ラジオの『Dwójka』はティエンヨウの演奏を絶賛し、評論家アンドジェイ・スウェクは次のように評している。「彼はソナタの中で“ポリフォニーの光”を見つけた。 声部の交差がこれほど自然に聴こえたのは稀だ。 彼の解釈は誠実で、真に知的だ。」また、批評家ロージャ・シフィアチュインスカも、「この曲が特に好きな作品ではない私でさえ、 彼のソナタには説得力を感じた」と述べている。さらに『Rzeczpospolita』紙は、「ティエンヨウ・リーは、この日の最も嬉しい驚きであった」と記し、その繊細な感性を高く評価した。
一方『Kurier Chopinowski』でも、彼の前奏曲群の扱いを“詩的でありながら明晰”と評し、若手ながら圧倒的な成熟を示したと伝えている。
インタビューでは彼自身がこう語っている。「ショパンを弾くたびに、音の奥に“沈黙”を探しています。 音が鳴り終わったその瞬間にこそ、 本当の音楽が生まれるのだと思います。」
この言葉が示すとおり、ティエンヨウ・リーの音楽は、単なる“演奏技術の完成”ではなく、沈黙の中に宿る祈り を描いた芸術そのものであった。——彼の未来は、すでに世界のどの舞台よりも明るく照らされている。
総括
3次予選へ進出する最有力候補はダヴィド・クリクリ、桑原志織、ヒョ・リー。次点でアダム・カウドゥンスキ、ヒョク・リー、シャオユ・フー、エリック・グオ、ティエンヨウ・リー。