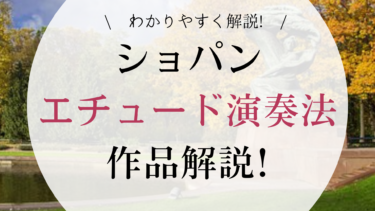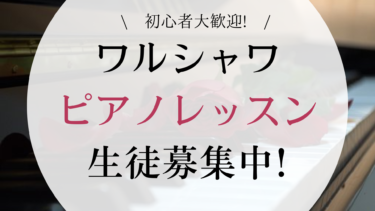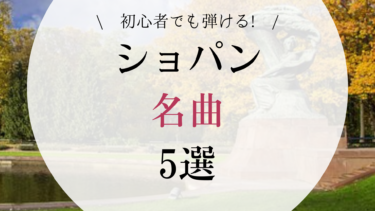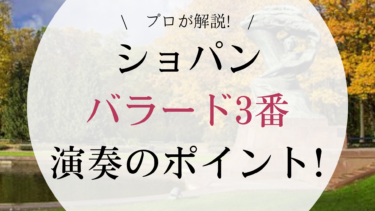この記事では、ショパンのエチュード(練習曲)の作品10の全12曲を、ショパン音楽大学在学のピアノ講師が作品解説いたします!難易度や演奏法なども、この記事でまとめました。
 こ~き
こ~きショパンのエチュードについて
ショパンが作曲した練習曲は、作品10と25のそれぞれ12曲ずつ、そして作品番号のない新練習曲が3曲の、あわせて27曲残しています。
このページでは、ショパンのエチュード作品10の全曲解説をいたします。
エチュード作品10について
前の曲との調性関係を見てみると、ショパンの意図がしっかりと読み取れます。
前の曲との調性関係
- 第1番 ハ長調
- 第2番 イ短調 (平行調)
- 第3番 ホ長調 (同主調の属調)
- 第4番 嬰ハ短調 (平行調)
- 第5番 変ト長調 (同主調の下属調)
- 第6番 変ホ短調 (平行調)
- 第7番 ハ長調
- 第8番 へ長調 (下属調)
- 第9番 ヘ短調 (同主調)
- 第10番 変イ長調 (平行調)
- 第11番 変ホ長調 (属調)
- 第12番 ハ短調 (平行調)
ショパンはバッハをとても尊敬しており、平均律クラヴィーア曲集を敬愛していました。
この作品10では、その平均律クラヴィーア曲集のような調性関係の構成を目指していたともいわれています。
作品10も平均律曲集と同じように、長調・短調と交互に構成するはずだと思いますが、7番と8番が長調で続いてしまっている部分は、予定通りにいかなかったのではないかと推測されています。
数年後に作曲したとされる「24の前奏曲」では、平均律曲集のようにすべて異なる調性で書かれています。
作曲の経緯
- 作品年: 1829年 (19歳)
ショパンは、ピアノ協奏曲を作曲し始めていた中、ショパン自身も協奏曲の演奏の難しさに嘆いていました。
そのような協奏曲という大作を作曲する過程で、
と思ったショパンは、練習曲の作曲をはじめました。
このエチュード作品10は、フランツ・リストに献呈されています。
“エチュード”名づけた経緯
“エクササイズ”?!
元々自分のために練習曲を作曲していたショパンは、当初この練習曲を「エクササイズ」と名付けていました。
しかし、世に出す際に「エチュード」(練習曲)と名付けたそうです。
元々練習曲といえば、技巧的な部分の問題点を改善するためのものとされていましたが、
ショパンは高度な技巧だけでなく、メロディーやハーモニーの美しさを重要視して、大作を演奏するうえで必要なあらゆる練習を取り入れたいと思い、このような美しく素晴らしい練習曲が完成しました。
作品解説
こちらでは、作品10と25のエチュードをそれぞれ1曲ずつ解説いたします!
作品10-1
難易度: 5.0
作品10-1は、人気アニメ「ピアノの森」のオープニング曲に使われているなど、最近特に演奏機会が多く人気な曲ですが、演奏者にとっては非常に難易度の高い曲です。
この曲は。右手は常に指と指の間を広げていなければならないため、特に手が大きく、指の長い方には比較的弾きやすいと思います。
この曲を練習することで、右手の拡張が出来るようになります。
中間部の短調の部分が特に技術的に難易度が高いため、まず最初のハ長調の部分から徐々にゆっくり練習していきましょう。
右手は、手先だけで弾き続けると途中で疲労が溜まってしまうため、手首や肘の脱力がとにかく大事です!
右手の上昇下降の際にクレッシェンド・ディクレッシェンドをつけることで音楽の幅を広げることができます。
また、和声変化が多いため、右手だけを聴くのではなく、左手のオクターブで和声変化を音楽的に表現することで、さらにコントラストを付けることが出来ます!
作品10-2
難易度: 5.0
作品10-2は、聴いているだけだと気付きにくいですが、個人的に最も難易度が高いと感じる曲です。
右手の3,4,5指の半音階によって上昇下降を繰り返す曲です。右手3,4,5指の独立を目指す曲ですが、それに加えて同時に、右手の1,2指の和声を弾くことが求められます。
①ゆっくり練習
テンポを落として、縦のラインをそろえることを意識して練習することをおすすめします。
②分けて練習
テンポを落とした状態で1,2指の内声と3,4,5指の半音階を分けて練習することも大事だと思います!
③指番号の工夫
楽譜に記載されている指番号を一つの参考としながら、自分に合った指番号を考えながら練習しましょう。
作品10-3 “別れの曲”
難易度: 3.5
日本ではテレビCMなどで多く使われているこの作品10-3「別れの曲」は、日本で最も有名なショパンの楽曲のひとつです。
ショパンのエチュードの特徴である、和声の美しさが光る一曲です。
日本人なら誰もが知っているこの名曲ですが、この曲を演奏するうえで最も重要なことは、メロディーラインを厳密なレガートで演奏することです。
ちなみに、この「別れの曲」という名前はショパンが名付けたわけではなく、ショパンを描写したドイツ伝記映画「別れの曲」 (1934年)でこの曲が使われたことで呼ばれているようです。
日本人の心も掴んだこの美しい旋律ですが、ショパン自身も献呈したリストに、「こんなに美しい旋律を、今まで書いたことがなかった」と言っていたようです。
①冒頭・最後
メロディーラインの厳密なレガート、内声は機械的にならないように演奏しましょう。
②中間部
冒頭のテーマの美しさを崩さないように、あくまでメロディックに演奏しましょう!
作品10-4
難易度: 4.0
求められる曲
作品10-4は、ショパンのエチュードの中で最も人気なエチュードのひとつです。
ドラマ「のだめカンタービレ」など多くの場面で演奏される曲のため、多くの人が憧れる一曲ですが、あらゆる技巧が求められる難易度の高い曲です。
右手も左手も高速な16分音符のパッセージが続き、小さいトリルなども出てくるため、両手の様々な技術が必要になります。
聴いてみると情熱的なロマン派音楽でしかないと思いますが、速い16分音符のパッセージが左右を交差するように登場するあたり、バッハ的な要素もある曲です。
表記されている強弱記号をよく見て、曲全体にコントラストをつけましょう。
テンポが揺れやすい曲のため、演奏する前に頭の中でテンポを決めたうえで、冒頭のアウフタクトを意識して演奏しましょう。
作品10-5 “黒鍵のエチュード”
難易度: 3.5
「黒鍵のエチュード」
黒鍵のエチュードも、演奏機会がやや多い練習曲です。
右手はほとんど黒鍵のみ打鍵する、演奏者にとってはとても変わった曲です。なお、左手はよく白鍵の和音が出てくる部分があります。
ショパンはこの曲に対して、「この曲は、黒鍵ばかり弾く曲だと知らなければ、なにも音楽性もないつまらない曲」と言っていたそうです。
技術的には、ほかのエチュードに比べるとそこまで難易度が高いわけではないのですが、しっかり粒が揃ったような音で弾くことがとても大事なため、決して簡単ではありません。
右手はバタバタさせずに、手のフォームがなるべく崩れないように弾きましょう。
グッと力んだら音が重くなるので脱力して華やかな音色を出すことを心がけましょう!
作品10-6
難易度: 3.0
習得するための練習曲
ショパンのエチュードの中ではあまり演奏機会のない曲ですが、音楽的な感覚が要求される練習曲です。
右手で旋律、左手で伴奏と、非常にシンプルなこの曲は技術的には最も易しい曲のひとつですが、音楽的には難易度の高い曲です。
暗い曲調の中でも、重苦しさや悲痛さといった、さまざまなネガティブな感情が入り混じっているようなイメージで弾くとよいでしょう。
演奏のポイント
機械的にならず、大きなメロディーライン、フレーズを感じながら演奏しましょう。
決して前のめりにならず、しかし流れをとめずに演奏することが大切です。
作品10-7
難易度: 4.5
ための練習曲
この練習曲の難易度は、手首の柔軟性や手の大きさ、指の大きさなどにより、人によって得意・不得意の分かれる曲です。
右手のメロディーラインを意識する必要があります。まずメロディーラインのみ練習してみてはいかがでしょうか。
右手ばかりにフォーカスを充てがちですが、左手で曲を引っ張っていくようなイメージで弾きましょう。
右手の細かい動きが平坦にならないようにすると、曲に高揚がつき、華やかさがつきます。
作品10-8
難易度: 4.0
ショパンコンクールでもよく演奏される曲のひとつです。
メロディーラインは左手ですが、右手の速い16分音符のアルペジオをいかに軽やかに弾くかがポイントです。
手首と腕の脱力を心がけましょう。柔軟な動きをうまく使って弾けると綺麗に聴こえます。
左手のリズムや強弱を表現豊かに演奏すると面白さが増します。
作品10-9
難易度: 3.5
左手首の柔軟性と、それぞれの指を広げるための練習曲です。
他のエチュードと比較するとややレベルは易しいため、最初に弾くショパンのエチュードとして選ばれることが多く、初めての方にはおすすめです。
左手の真ん中の指を起点に、左右にスライドさせるように演奏しましょう。
その際に左手の親指のラインと右手のメロディ両方をハモるように弾きましょう
作品10-10
難易度: 5.0
のための練習曲
とても華やかなこの曲ですが、非常に難易度の高い練習曲のひとつです。
中間部の転調部分は技術的に演奏が特に難しいですが、音楽的には最大のポイントな部分です。
技術的な面に限らず、音楽的にも非常に評価されている、隠れ名曲のひとつです。
右手のアクセントの場所とフレーズ、アーティキレーションが変化する曲なので、よく把握してフォームを崩さずに演奏しましょう。
作品10-11
難易度: 3.0
アルペジオの練習曲
この曲は、両手の幅広いアルペジオを美しく奏でるための練習曲です。
まるでハープのような流れる音色を奏でられたら最高ですね!
腕と手首の柔軟さを意識しながら、メロディーラインが途切れないように歌って弾きましょう。
作品10-12 “革命”
難易度: 3.5
ショパンが残した楽曲の中で最も有名な曲のひとつ「革命のエチュード」。
ショパンの祖国ポーランドがロシアに支配されていた当時、ショパンは周囲の勧めでポーランドを離れていました。
そんなさ中、ロシア軍に対する革命に失敗してポーランド軍が鎮圧されてしまいました。
家族や友人が殺されてしまうのではないかという不安や怒りの感情で、荒れ狂ってピアノに向かっていたショパン。
そんな中できた曲がこの「革命のエチュード」なのだそうです。
この曲は右手の主題が非常に有名ですが、主に左手の速い16分音符のアルペジオのための練習曲です。エチュードの中で唯一序奏のある楽曲です。
右手の有名な主題を引っ張っていくように左手の練習が特に重要です。
特に左手は手首を柔軟にして演奏しましょう。
難易度まとめ
| 作品番号 | 難易度 |
| 10-1 | 5.0 |
| 10-2 | 5.0 |
| 10-3 (別れの曲) | 3.5 |
| 10-4 | 4.0 |
| 10-5 (黒鍵のエチュード) | 3.5 |
| 10-6 | 3.0 |
| 10-7 | 4.5 |
| 10-8 | 4.0 |
| 10-9 | 3.5 |
| 10-10 | 5.0 |
| 10-11 | 3.0 |
| 10-12 (革命のエチュード) | 3.5 |
楽譜
ショパンの楽譜の選び方
エキエル版
信頼性のある原典版が1冊あるといいと思います。
エキエル版は、長年研究や多くの資料を参考にして作られており、ショパンの意図に最も近い楽譜と言われています。ショパンをしっかり勉強したいピアニストや音大生の方などにはおすすめです。
パデレフスキ版
校訂版であるパデレフスキ版は、多くのピアニストが使っており、代表的なショパンの楽譜といえばパデレフスキ版ともいわれていました。
無料楽譜
ちらっと楽譜を見てみたい!という方は、楽譜が無料で閲覧することが出来ます。IMSLPというサイトでは、さまざまなクラシック音楽の楽曲の楽譜を閲覧することが出来ます。